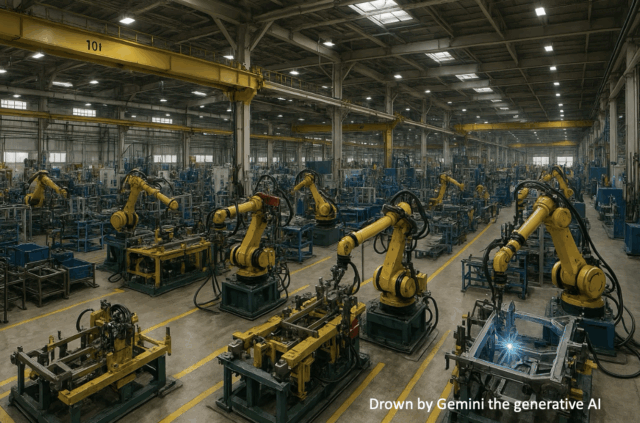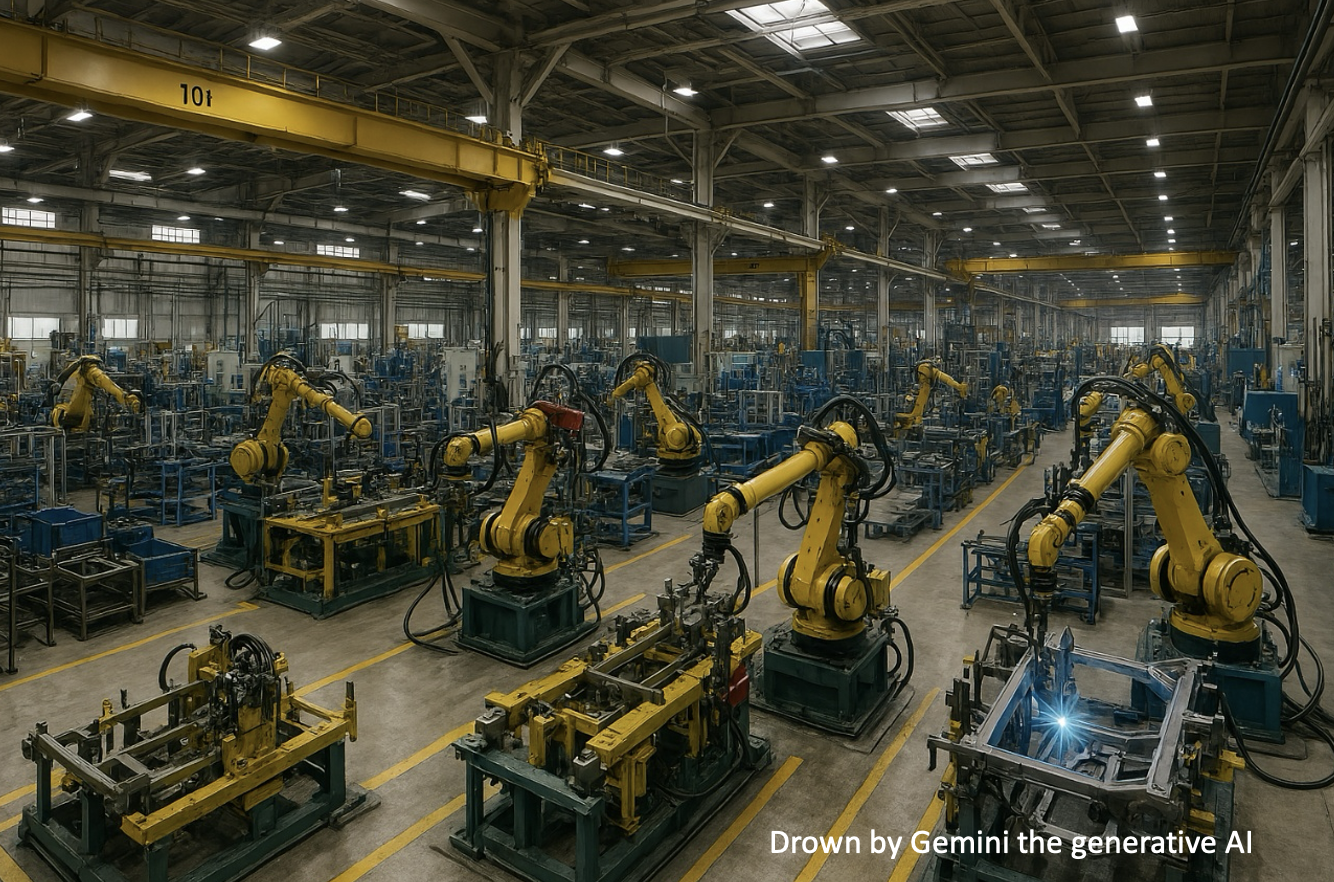効率化と品質向上を目指す構内物流標準化マニュアル 第2回〜入荷作業の標準化

工場の入り口としての入荷作業
入荷作業はサプライチェーンにおいて工場の入り口をコントロールする作業である。ものづくりの第一歩は生産に使用する部品や資材(以下、部品等)を調達すること。構内物流の仕事として発注行為がある。納品時には発注通りの部品等を確認するとともに受け入れることになる。これが入荷作業である。
具体的には、正しい部品等が、正しい数量、正しい品質で納入されたことを確認し、その証として受領書に受領印を押して納入業者へ手渡す。中小受託取引適正化法(旧下請法)では原則として受領したものを返品することは禁止されている。だからこそこの工程は慎重に実施することが求められる。不良を見逃して工場に搬入してしまっては手遅れである。誰が行っても同じ結果となるように標準化を実施していこう。
入荷作業の作業要件整理
標準化に先立ち、各工程の作業要件を洗い出しそれを「作業要件一覧表」にまとめておきたい。物流作業における作業要件には「品質基準」、「必要機器」、「必要知識」、「必要技能」、「習熟の難易度」、「習熟必要期間」の6項目がある。入荷作業についてこの6項目を洗い出してみよう。

図1に例として挙げてみた。この中で「必要知識」として製品知識と製品番号の読み方を入れてある。このような必要知識については何を使ってどのような方法で教えていくのかについても定めておく必要がある。習熟期間30日の中で教育計画を作って実行していこう。
入荷作業の標準作業
構内物流作業は多少手順が違っても見かけ上の結果が同じになることがある。たとえば運搬時に通る通路が異なったとしても目的地には到達できるようなケースだ。このような自由度が高い作業ゆえに標準化が遅れ、効率や品質に影響が出ていると考えられる。
入荷作業でも作業員全員が標準作業として定められた通りに実行することで目的通りの効率と品質を確保したい。標準作業書の主なステップと急所の例を図2、3に示した。重要なことはできるだけ急所を詳しく記すことにある。その目的は作業者の恣意性を排除することで物流品質低下を防ぐことにある。


特に図3に記したように「文章」と「写真(絵)」を合致させ、誰が見ても一瞬で理解できる工夫が必要だ。ここでは入荷作業で必須となる「3点照合」についての例を示してある。同様に「発注書」のどの部分と「納品書」のどの部分を見比べて未納の有無を確認するのか、「箱つぶれ」や「製品瑕疵」の例にはどのようなものがあるのか等を「写真(絵)」で示すことが望ましい。
標準作業書には「禁止事項」についても示しておきたい。図3では照合時には黙読を禁止する旨記してある。
さらに当工程における「異常の状態」と「異常を発見した時の処置」についても記しておこう。入荷作業での例を1つ挙げてみよう。異常とは「納品書の数量」と「現品の数量」が合致しないこと。それを発見した時の処置として以下のルールを定める。「①納入業者と確認し、納品書の数量を変更し、サインをもらう」、「②上司へ報告するとともに、部品管理責任部署へ連絡する」。製品瑕疵を発見した場合には勝手な判断をせずにTYK(仕事を止める、上司を呼ぶ、指示を待つ)を徹底させることなどをきちんと記しておくことが重要だ。
いかがだろうか。例に示したこと以外にも入荷作業ではいくつもの留意点が考えられると思われる。標準化の判断基準として「作業者が勝手な判断をする余地を与えないこと」と考えれば精度の高い標準作業が組み立てられるだろう。
【第2回まとめ】
- 入荷作業では、正しい部品等が、正しい数量、正しい品質で納入されたことを確認する。
- 中小受託取引適正化法(旧下請法)では原則として受領したものを返品することは禁止されているので、入荷作業は慎重な対応が求められる。
- 最初に入荷作業で必要要件6項目について整理しよう。
- 標準作業書には急所を詳しく記載しよう。作業者の恣意性を排除することがポイントだ
- さらに入荷作業時の禁止事項、異常の状態とその処置についても明記しておこう。
この記事の作者
仙石 惠一
合同会社Kein物流改善研究所 代表社員