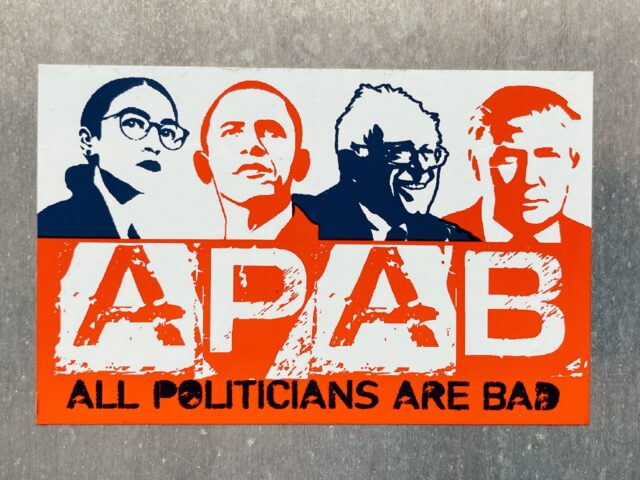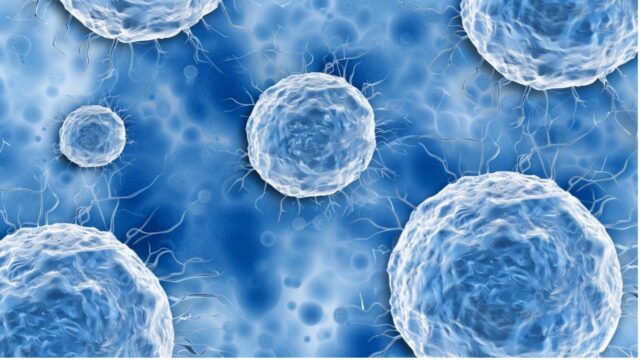物流博物館の紹介と設立の経緯について

<物流博物館とは>
私が勤務する物流博物館は、1998年8月に日本で唯一の物流専門の博物館として東京・港区高輪に開館した。私はこの前年に別の博物館から転職し、建設準備の途中から参画したので、この職場に来て今年で早いもので28年目となる。
物流博物館は延床面積823㎡とかなり小規模の博物館ではあるが、物流について広く一般の方々に関心を持っていただくことを主な目的として設立された。館内には物流の歴史と現在に関する2つの常設展示室のほか、映像上映・講演会・展示などを行う多目的の展示室、図書閲覧室を備え、収蔵資料も文書史料、実物資料、図書類、物流現場を記録した各時代の写真や映像資料など、物流に特化したコレクションを形成しており、ユニークな専門博物館と自負している。
ちょうどこれからの季節、4月から5月にかけては、多くの物流関係企業の新入社員研修でのご利用が盛況を迎える時期となる。こうした団体見学に際しては、どんなに少人数でも、ご希望があれば学芸員が映像などを用いたレクチャーや展示のご案内を行っている。物流の過去と現在、とくに戦後の物流発展の歴史的経緯について、比較的短時間で概観できるよう配慮させて頂いているつもりである。物流関係企業でその職業的人生の第一歩を印され、これから忙しく物流現場の現実と向き合っていく皆さんに、とくに先人たちの努力の軌跡を知っていただき、社会に貢献してきた業界の過去の歩みに触れていただくことにより、記憶に残るような何がしかの感想を抱いていただければと考えている。

中学校の修学旅行生が職業研究の一環として、当館を訪問することも多い。開館から10年くらいは、小学校5年生の社会科見学での団体利用も多かったが、近年は小学校の団体見学はほぼ姿を消した。しかし来館者は増加している。これは個人入館者が増えるようになったことが大きい。コロナ禍の数年前くらいから、こうした傾向が目立つようになった。ことに若い世代や女性の来館者が目に見えて増えてきているのが近年の特徴である。格別知名度が高いわけでもない小規模館、それも限定された内容のテーマ館に、わざわざ足を運んでくださる方々が増えているというのは、本当にありがたいことだと思っている。SNSやネット情報の影響力のほか、とくに物流に対する社会の関心の高まりを強く感じている。
<物流博物館の特徴>
当館は小規模館なので、逆に比較的短時間で物流の過去と現在に触れることができるという点も、実はメリットといえるのかもしれない。「物流の歴史」展示室では、原始・古代から現代に至る物流の歩みの概観のほか、江戸時代以降1970年代までの物流の歩みを、各種資料や模型などで紹介している。「現代の物流」展示室では、物流産業の概要やテーマごとの展示のほか、陸海空の物流ターミナルの大型ジオラマや各種模型、クイズやゲームなどを通じて、楽しみながら物流に親しんでいただけるように工夫しているつもりである。物流に関する過去や現在の数多くの映像を、館内各所に設置されたモニターで視聴できる点も当館の特徴のひとつだろう。また、「現代の物流」展示室の体験コーナーには、「運ぶ」をテーマにした70冊ほどの絵本があり、ジャンボ物流パズルや塗り絵、トラックやフォークリフトのおもちゃを使ったごっこ遊び、物流企業各社の制服着用体験なども楽しむことができる。そのほか、江戸時代の飛脚衣装の着用体験、昔の運ぶ道具体験、風呂敷包み体験など、「運ぶ」に関する体験的な各種展示を用意している。欲張りではあるが、年齢層や各人の関心に応じた楽しみ方ができるような館でありたいと考えている。
当館では、年に1回テーマを決めて特別展や企画展を開催しており、これにはとくに力を入れている(今年度は常設展示の模様替えのため開催はなし)。館内で行われるイベントは、毎月1回行っている映画上映会、毎年夏休み期間中に開催する段ボール工作やペーパークラフトイベント、クリスマスが近くなると、サンタクロースも物流事業者ということで、小さなお子様向けにサンタをテーマにした映画会を開いたり、最近ではJR貨物音楽部の皆さんにご協力を頂き音楽会を開催しているほか、貨物列車に力を入れた鉄道模型運転会なども催しており人気である。また、江戸時代の交通や物流に関わる古文書を読む初級・中級の連続講座のほか、月2回の古文書勉強会なども20数年間続いており、幼児から高齢者まで、さまざまなご関心をもつ方々を念頭に置きながら、いろいろな催しを企画している。
<物流博物館設立の経緯>
このように物流全般について多角的に取り上げ、紹介している当館ではあるが、その一方で、NIPPON EXPRESSホールディングス㈱とグループ企業の企業博物館という側面も持っている。展示やイベントでは企業色は極力出さないというのが設立当初からの方針ではあるが、企業博物館として、企業資料の保存・公開という責務も担っている。
実は当館には前身となる施設があった。1958年、丸の内の大手町ビルに日本通運㈱本社が移転した際、同社本社内に開室した「通運史料室」がそれである。その後、1962年に同社本社が秋葉原に移転するのに伴い、同史料室も秋葉原本社ビル4階に移った。やがて時を経て1987年には同史料室の運営が財団法人小運送協会に委託されるとともに、展示を社史の紹介から交通・運輸に関するより広い内容に変更し、名称も「物流史料館」と改めた。
「物流史料館」を運営した小運送協会というのは、戦時下の1938年に、当時半官半民の国策会社だった日本通運の出捐によって設立された財団である。「小運送」とは鉄道や海運といった「大運送」に対し、駅や港から先の輸送や輸送のコーディネートなどを行う業務をさす言葉で、明治期に自然発生的に使われるようになった。のち、1937年には「小運送業法」という法律も制定されている。日本通運は小運送業を統括するため、同年に制定された「日本通運株式会社法」に基づき設立された企業だった(両法とも1950年廃止)。小運送協会は戦時下にあって、業界関係者の教育施設の運営や共済事業を行っていたが、戦後は学生寮の運営などを主要な業務としていた。しかし、「小運送」というのはさすがに古い言葉だったので、1994年には財団法人利用運送振興会と改称、その後、物流史料館は閉館し、この財団が現在地に物流博物館を新たに建設、運営を行うこととなった。なお、同財団は公益法人制度改革によって2012年には公益財団法人となり、今日に至っている。
このような経緯から、物流博物館には、NIPPON EXPRESSホールディングス㈱とグループ企業の歴史的な企業資料が集中的に保存されている。通運史料室発足時に、全社を挙げて歴史的資料を収集し、また、日本通運が1962年に刊行した社史を編纂する際に収集した資料もこれらに加わり、現在のコレクションの中核が形作られた。その多くは日本通運の社史に関する資料であるが、江戸期以降の交通・運輸に関する資料も、購入などにより積極的に収集されていた。近年では同社の専門図書館の閉館に伴い、中心的な蔵書が当館に移管されている。

1958年に通運史料室を開室した理由については、企業のステイタスの向上という目的が第一にあったようだ。当時、日本通運は設立されて20年ほどの企業だったが、その前身企業である内国通運会社は1872(明治5)年の創業であり、さらにはこの企業を設立した飛脚問屋仲間の歩みまで視野に含めれば、17世紀後半以来の歴史を持つ。当時としては、財界などで、こうした長い歴史をもつ企業である点を強調するメリットがあると考えられていたようだ。同時に、時代の急激な転換期にあって、散逸しやすい業界資料の収集を一定の危機感のもと意識的に行ったことには、今日から見て大きな意義があったといえると思う。
これに対し、1998年に物流博物館として新たに開館した理由は、それまでの展示の陳腐化・老朽化に加え、背景としては、当時、宅配便が人々の生活に定着し、「物流」が一般の人々にとっても身近に感じられる機会が増え、また小学校5年生の社会科の単元でも「運輸」が取り上げられるなどの動きがあったことが挙げられる。同時に、物流産業の正当な社会的地位や適正な物流コストなどへの無理解が当時すでに問題視されており、こうした現状に対する物流企業側の取り組みのひとつとして、博物館建設が立案されたという経緯があった。 その意味では、とくに昨今の情勢を踏まえ、当館の果たすべき役割についても、さらに新たな展開を考えるべき時期に来ているのではないかと個人的には考えている。
物流博物館にお越しになったことがない方だけでなく、すでに来館されたことのある方にも、ぜひとも当館を訪れていただき、いろいろなご意見やご感想をお聞かせいただければ、大変ありがたいことと思っている。皆様のご来館をお待ちしております。
この記事の作者

玉井 幹司
物流博物館主任学芸員